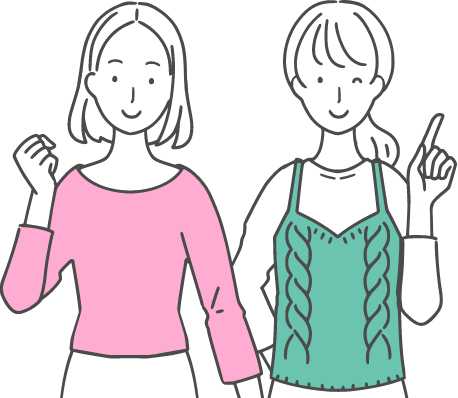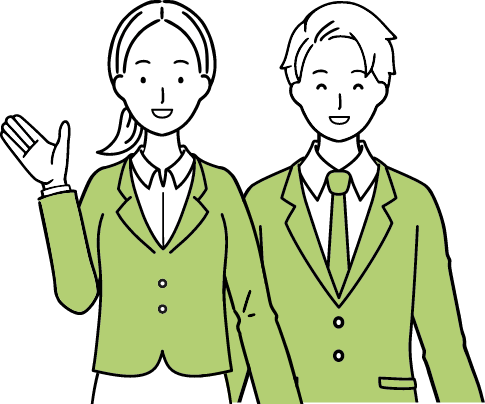オペレーティングリースとは、ファイナンスリース以外のリース取引全般を意味します。
一般的には、車や航空機、事業用物件などの資産の貸し借りを目的に、オペレーティングリース取引は行われます。
しかしオペレーティングリース取引は、投資や節税目的で利用されることもあります。
投資や節税によるメリットを得る目的で行われるものは、「日本版オペレーティングリース取引」と呼ばれます。
今回の記事では、そんな日本版オペレーティングリース取引とは何なのかを、ファイナンスリースや通常のオペレーティングリース取引との違いを明確にしつつ解説します。

AFP(日本FP協会認定) / MDRT成績資格会員(COT)
この記事の監修担当者:渋谷幸司
新卒で大手鉄鋼商社に入社。5年半、日本を支える鉄鋼企業と世界の橋渡しに尽力した後、2015年外資系大手生命保険会社に転職。転職後も前職のお客様を金融業の側面から支えたいという想いで奮闘した。
日々取り組んでいく中で、世界情勢の変化や、日本社会の制度改定、お客様の思考変化を察知し、自身の事業変革を決断。
2018年大手上場金融代理店に入社し、生命保険業においてはMDRT、COT成績資格会員と実績を伸ばしつつ、所属会社で扱っていないDC(確定拠出年金)などを自ら会社の枠を超えて代理店契約するなど勢力的に活動。現在は保険営業マン向けのセミナー講師を務め、「先生」として同業者から熱い信頼を受けている。
個別相談のご要望も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
オペレーティングリースとはどんな仕組み
オペレーティングリースとは、ファイナンスリースの持つ「解約不能」と「フルペイアウト」の要件をいずれかまたは両方を満たさないリース取引です。
つまり、中途解約が認められていたり、借手が資産の実質的な所有権を持たないリース取引です。
具体的な仕組みは、一般的な資産のレンタルとほぼ同じです。
貸手が購入したリース資産を、借手が定期的にリース料を支払うことでレンタルすることで、オペレーティングリース取引が成立します。
借手会社から見ると、ファイナンスリースよりもリース料の総額を抑えられる点や、リース資産を貸借対照表に計上する処理を行わずに済む点がメリットとなります。
一方の貸手会社は、定期的にリース料を受け取れる点や、リース期間が終了した後に、資産を売却することで利益を得られる点がメリットとなります。
なお現行の日本会計基準では、通常の賃貸借処理で仕訳を行うことになっています。
借手の会社は、リース料を支払うタイミングで借方にリース料、貸方に支出する現金を仕訳する形で処理します。
一方で貸手は、借方に受け取った現金、貸方に収益として受取リース料を仕訳処理します。
ただし最新の国際会計基準(IFRS)では、オペレーティングリース取引でも、借手側が資産を計上する決まりとなっています。
今後日本の会計基準も、この方針を適用することになる可能性が高いため注意しておきましょう。
投資や節税対策で利用されるのは貸手側の取引
そもそもオペレーティングリースとは、本来は借手と貸手間での事業用資産のレンタルです。
しかし貸手側の会計処理を応用すると、投資による利益や節税のメリットを得られます。
なぜ投資や節税対策で利用できるかを理解するために、まずは貸手会社の視点からオペレーティングリース取引の流れを確認しましょう。
貸手視点で見ると、オペレーティングリース取引は下記の仕組みで行われます。
- 投資したい法人から出資を募る
- 出資された資金を使って、リースする物件を購入する
- 購入した物件を借手にレンタルする
- 定期的に借手からリース料を受け取る
- 受け取ったリース料を投資家に分配する
ここで重要なのは、あくまで貸手の会社はリース物件を「レンタル」しているに過ぎない点です。
物件の所有権は貸手会社に残るため、貸手側では減価償却費を計上する会計処理を行わなくてはいけません。
航空機などの高額な資産を定率法で減価償却した場合、購入後から数年は多額の減価償却費を計上します。
その結果、しばらくはリース料の収入を減価償却費が上回り、赤字が計上されることになります。
この貸手会社が計上する赤字こそが、投資家に節税効果をもたらします。
なぜなら、投資した側の会社でも、出資先(貸手)が計上した赤字を損益計算書に計上できるからです。
貸手が計上した赤字分を自社の損益計算書でも認識することで、投資した側では事業で得られた利益を減らすことができます。
その結果、納税する税金の額が減るわけです。
また投資した会社は、リース料の一部を持分の割合に応じて受け取ることができます。
そのためオペレーティングリース取引は、投資商品としてのメリットも大きいと言えるでしょう。
日本版オペレーティングリースと呼ばれる理由
投資や節税目的で貸手側に出資する場合、レンタル目的の取引と区別して「日本版オペレーティングリース」と呼ばれます。
ではなぜ、日本版オペレーティングリースと呼ばれるのでしょうか?
結論から言うと、日本の商法に規定されている「匿名組合」が貸手となることが、日本版オペレーティングリースと呼ばれる理由です。
匿名組合とは、匿名組合員が営業者に出資を行い、対価としてその営業で得られた利益の分配を受けることが約束される契約の形態です。
つまり日本版オペレーティングリースとは、営業者(貸手)が複数の匿名組合員(投資家)から出資をしてもらい、そのお金で航空機などのリース物件を購入・レンタルする取引というわけです。
一方で、リース会社が自己資金や借入などを基に事業用物件をレンタルするケースは、通常のオペレーティングリースとなります。
人気の高い投資物件の対象とそれぞれの特徴
日本版オペレーティングリース取引では、主に「航空機」、「船舶」、「コンテナ」が投資物件の対象として人気を集めています。
それぞれの物件は、投資するメリットやデメリット、リース期間、投資額などに大きな違いがあります。
そこでこの章では、投資・節税目的のオペレーティングリースにおいて、人気の高い3種類の投資物件の特徴について、違いを分かりやすく解説します。
航空機
日本版オペレーティングリース取引において、最もおすすめの投資物件なのが「航空機」です。
航空機をオススメする最大の理由とは、需要の高さです。
世界的に人口が増加するにつれて、観光やビジネスなどで航空機に登場する人数も増加傾向にあります。
そのため、リース料の分配を確実に得やすいです。
また、売却時には高い値段で売却できる可能性が高いため、売却益の分配で得られる利益も多い傾向があります。
加えて、数あるリース物件の中でも購入価格が高い分、減価償却費として計上できる金額も大きく、節税効果も大きくなりやすいです。
このように航空機には、数あるリース物件の中でもメリットが多くあります。
しかし一方で、投資するにあたってはいくつか注意点もあります。
最大の注意点は、急な技術革新などにより物件の中古価格が下落する可能性がある点です。
リース期間が満了した時点で、想定よりも安い値段でしか売却できず、結果的にほとんど収益を分配してもらえないリスクがあります。
またリース期間が7年〜10年間と、数あるリース資産の中でも長期にわたる点にも注意しましょう。
投入した多額の資金をしばらくは動かせなくなるため、長期的視点での運用が求められます。
船舶
船舶の特徴とは、一言で表すと「中古市場における値動きの激しさ」です。
その理由の1つには、航空機と同様に技術革新による価格の下落があります。
それだけでなく、船舶の需要はバルチック海運指数と呼ばれる指標により決まることも要因となっています。
このバルチック海運指数は短期間で大きく変動するため、その分船舶の売買価格も大きく変動します。
こうした理由から、タイミング次第では想定よりも安い値段での売却となり、投資家が得られる収益も少なくなるリスクがあります。
また、リース期間も6年〜10年と比較的長く、短期的に資金を移動できない点もリスクとなり得ます。
加えて、最低出資額も3,000万円から5,000万円と比較的大きいです。
5年以上にわたって数千万円もの資金を動かせない点は、経営者にとってはリスク以外の何物でもありません。
以上のように、リース物件としての船舶にはあまり魅力的なメリットがありません。
投資や節税目的で投資する場合、船舶よりは他の物件(航空機など)を投資対象として選ぶのがオススメです。
コンテナ
コンテナとは、貨物の輸送に用いられる容器の一種です。
オペレーティングリース取引においては、最低限必要となる出資額が少ない点が大きなメリットです。
航空機や船舶などの一般的なリース物件の場合、最低でも3,000万円〜4,000万円ほどの出資が必要となります。
一方でコンテナが投資対象の物件だと、大体1,000万円から投資できます。
リース期間も5年〜6年と比較的短いため、あらゆるリース物件の中でも、投資で負うリスクは小さいと言えるでしょう。
また、他のリース物件とは違い、技術革新の頻度が少ない点も魅力の一つです。
前述した通り、技術革新の頻度や度合いが大きい物件を用いたオペレーティングリースに投資すると、価格下落により売却時に大きな収益を得られなくなります。
一方コンテナの場合、技術革新による大幅な価値の下落が生じにくいため、売却時に大きな損失をこうむる可能性は低いです。
以上の理由よりコンテナは、少ない資金でオペレーティングリース取引に投資したい方や、なるべく短期間でオペレーティングリースへの投資を行いたい方、低リスクでの投資を行いたい方にオススメのリース物件と言えます。
反対に、ある程度長い期間を使いたい方や、大きな節税効果や利益を得たい方には、航空機を使ったオペレーティングリース取引に投資するのがオススメです。
活用したい具体的なケースとは
日本版オペレーティングリース取引は、いったいどのようなケースで活用できるのでしょうか?
節税や投資目的で行うオペレーティングリース取引では、主に下記2つのケースで大きなメリットを得られます。
利益の繰り延べを行いたい
オペレーティングリースは、利益の繰り延べたい場合にとても効果的な取引です。
利益の繰り延べとは、今期に計上すべき利益を来期以降に先送りにする会計処理の手法です。
たとえば保険商品に加入し、保険料の支払い代金を損金計上することで、その年度の利益を減額し、本来払うべき税金を支払わないようにする手法が、利益の繰り延べと呼ばれます。
「利益の繰り延べ」と呼ばれるのは、解約時に多額の利益を受け取ることで、そこに多額の税金がかかるためです。
実は先ほどご説明したオペレーティングリース取引への投資も、利益の繰り延べに用いる手法です。
保険とは違い、減価償却費を計上する処理や有価証券の処理の仕組みを使い、利益の繰り延べを実現します。
オペレーティングリースにより利益の繰り延べを行うことで、本来支払うべき税金を後回しにするメリットを得られます。
ただし、単純に繰り延べを行っただけでは、リース物件の売却時に多額の税金がかかる恐れがあります。
リース期間が完了した時点で節税効果を得るには、その時点での「出口戦略」を検討しておくことが大切です。
たとえばリース物件の売却で得られた分配金を、退職金や設備投資などの費用として用いれば、その年度の利益を減らすことが可能です。
その結果、納税する金額を減らせる上に有益な用途で資金を活用できるため、節税に成功したと言えます。
オペレーティングリースに節税目的で投資する場合は、リース期間中の利益の繰り延べだけでなく、期間終了後の出口戦略も合わせて考えておきましょう。
事業継承を行いたい
オペレーティングリース取引の会計処理を応用すれば、事業継承でかかる税金の節税メリットも得られます。
事業継承では、先代経営者から後継者に自社株を移転する形で、経営権の承継を図ります。
しかし自社株を移転すると、多額の贈与税または相続税がかかる可能性があります。
そこで有効となるのが、オペレーティングリース取引に特有の会計処理です。
前述した通りオペレーティングリースでは、リース期間の当初に多額の減価償却費(損金)を計上する処理を行います。
多額の費用を計上する会計処理を行うことで、自社株の評価額を目減りさせる効果が期待できます。
つまり、評価額が目減りしたタイミングで自社株を継承すれば、結果的に納税額を大幅に減らすことができるのです。
また、リース物件の売却時に得られた収益を先代経営者の退職金として用いれば、その時点でも節税効果を得られます。
まとめ
本来オペレーティングリース取引とは、事業用資産の賃貸借を目的に行うものです。
しかし、オペレーティングリース取引で貸手が行う会計処理を応用すれば、リース物件への投資による利益や節税のメリットを得られます。
オペレーティングリースの投資物件は航空機や船舶など多岐に渡るため、ご自身の計画や希望に合う物件に投資することがベストです。
これまで単純な資産の賃貸借としてオペレーティングリースを考えていた方も、ぜひ投資や節税目的でオペレーティングリースを活用してはいかがでしょうか?