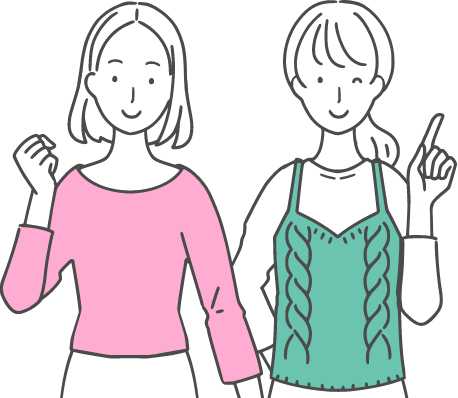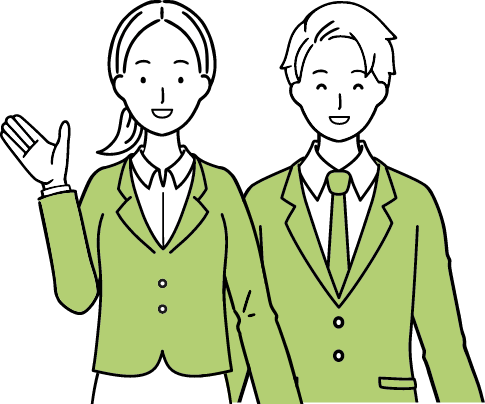ファイナンスリース取引の場合、借手側でリース資産の減価償却を行い、貸手側では必要となりません。
一方でオペレーティングリース取引は、ファイナンスリースと違い賃貸借(レンタル)処理を行う決まりとなって居ます。
売買取引として会計処理を行うファイナンスリース取引とは、減価償却の取り扱いや方法が大きく異なります。
そこで今回は、貸手企業側の視点からオペレーティングリース取引における減価償却の取り扱いをお伝えします。
減価償却の方法のみならず、節税対策になる理由や、投資対象別に耐用年数も解説します。

証券外務員 / ファミリービジネスアドバイザー
この記事の監修担当者:櫻井浩介
日系大手証券会社を経て、顧客第一主義を極めるために2018年に独立。高所得法人やそのオーナー一族をクライアントに持つ。
主な業務は、資産管理。また、弁護士、税理士、会計士などのプロフェッショナルと協働して、様々な事業承継案件や事業再生案件等、クライアントの持続的発展のためのサポートを多岐に渡っておこなっている。
証券会社時代の経験に基づく資産運用、節税対策などの幅広い経験と知識に裏付けられた誠実なアドバイスは、資金面に悩む顧客から絶大な信頼を得ている。
個別相談のご要望も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
減価償却とは?会計処理や取扱いについて
減価償却とは、長期的に使用する資産の購入費用を、資産を利用する期間(耐用年数)内で分割した上で計上する会計処理です。
オペレーティングリース取引は、前述したとおり賃貸借(レンタル)取引があったものとみなして、会計や税務の処理を行う決まりとなっています。
リース資産を借り手にレンタルしているに過ぎないため、貸し手企業が購入した資産の減価償却を行います。
一方の借り手企業は、資産の所有権を取得したわけではないため、減価償却を行う必要はありません。
新リース基準ではオペレーティングリースの借り手側も資産計上が必要
2019年以降、国際財務報告基準「IFRS」を適用する企業では、新リース会計基準に基づいてオペレーティングリース取引の会計処理を行う決まりとなっています。
貸し手会社の会計や税務の処理は、従来どおりとなるため特に問題はありません。
一方で借り手企業では、オペレーティングリース取引の開始時点に、「使用権資産」という形で、リース資産を仕訳する決まりとなりました。
それに伴い、貸手側の法人でも使用権資産の減価償却が必要となっています。
IFRSに準拠している会社とそうでない会社で、オペレーティングリース取引の会計処理に違いが生じている点は、念のため注意しておきましょう。
日本型オペレーティングリース取引は減価償却費で節税対策
事業用資産の賃貸借で用いられるオペレーティングリース取引は、節税対策での投資対象となる場合もあります。
節税対策となるオペレーティングリース取引は、日本型オペレーティングリース取引と呼ばれます。
日本型オペレーティングリース取引の持つ最大の特徴は、日本の商法で規定された「匿名組合」が貸手となる点です。
この匿名組合は、節税を図りたい法人から受けた出資金を基に、リース資産を購入します。
投資した企業側は、出資割合に応じて貸手が得られた損益の一部を受け取ります。
この章では、そんな節税に役立つ日本版オペレーティングリース取引について、会計や税務の処理方法、節税対策となる理由などを解説します。
処理の方法
会計や税務処理の方法を理解するには、まずは減価償却費の金額を算定する方法を知らなくてはいけません。
減価償却費は、「定額法」または「定率法」と呼ばれる方法で算出するのが一般的です。
特にオペレーティングリース取引の場合は、定率法を採用することが多いです。
定率法とは、まだ減価償却を行っていない固定資産の金額(未償却残高)について、毎年一定割合の減価償却費を計上する方法です。
計算の仕組み上、固定資産を購入した時点に近いほど、計上する減価償却費は大きくなります。
定率法では、1年間の減価償却費を下記の計算式で求めます。
- 減価償却費 = 未償却残高(帳簿価額) × 償却率
たとえばリース資産が50,000千円、償却率が0.286の場合、1年目〜3年目の減価償却費は下記の通り計算できます。
※計算を簡略化するために、改定償却率と保証率は考慮していません。
- 1年目:50,000千円 × 0.286 = 14,300千円
- 2年目:(50,000千円 − 14,300千円) × 0.286 = 10,210.2千円
- 3年目:(50,000千円 − 14,300千円 − 10,210.2千円) × 0.286 ≒ 7,290千円
なお償却率は、リース資産の耐用年数(利用に耐えられる年数)によって異なります。
耐用年数に関しては、後ほど詳しく解説します。
次に、具体的な会計や税務処理の方法をお伝えします。
オペレーティングリース取引の貸手企業は、借方に減価償却費、貸方に減価償却累計額を仕訳する形で、減価償却の処理を行います。
| (借方) 減価償却費 100千円 | (貸方) 減価償却累計額 100千円 |
なお支払った減価償却費は、税務上その年度の損金として計上します。
会計や税務の処理自体は、通常の取引における減価償却と同じなので、特段説明することはありません。
減価償却費が節税対策になる理由
日本型オペレーティングリースは、前述したとおり出資者の節税対策になります。
オペレーティングリース取引が節税対策になる理由は、「貸手側が計上した減価償却費を、出資した会社側でも認識できるから」です。
日本型オペレーティングリース取引において、貸手である匿名組合は、出資者から集めた資金を使ってリース資産を購入します。
そして購入したリース資産の費用は、減価償却費として一定期間にわたって計上されます。
ところでオペレーティングリース取引では、購入初期ほど大きい額を計上する「定率法」によって、減価償却費を計上するのが一般的です。
また、購入するリース資産は高額な資産(航空機やコンテナなど)であるため、計上する減価償却費も大きな額となります。
つまり貸手企業側は、日本型オペレーティングリース取引を始めてから1〜2年間は、多額の減価償却費(リース資産の70%〜90%程度)を計上することとなります。
貸手である匿名組合に投資した法人は、出資金を「有価証券」として会計処理するルールとなっています。
このルールがあるため、投資家側でも当初1〜2年間は多額の損金を計上できます。
多額の損金と事業で得られた利益を相殺し、大きな節税メリットを得られる仕組みとなっているわけです。
内部留保の効果
日本型オペレーティングリース取引による節税は、内部留保を蓄積するメリットももたらします。
内部留保とは、企業が生み出した利益から税金や役員報酬、配当金などを差し引いたもので、会社内に蓄積されるものを意味します。
内部留保は、企業の設備投資や業績悪化時の蓄えとして不可欠であり、いわば企業の体力を表すものです。
オペレティングリース取引で計上する減価償却費は、会計や税務上は費用(損金)として計上するものの、実質的な現金の支出は伴いません。
つまり減価償却費を計上しても、実質的に手元に残る利益は減らさずに済むため、内部留保を貯める効果が得られるわけです。
貸手は税務や会計上は赤字を計上しながら、実質的には内部留保を増やし続けることができます。
そのため、一見すると赤字を計上していて危ないように見えますが、実際にはかえって会社としての体力は着々とついているのです。
耐用年数の期間はオペレーティングリースの投資対象によって異なる
減価償却費を計算するには、投資対象の耐用年数を知っておくことが不可欠です。
そんな耐用年数ですが、出資対象のリース資産によって異なります。
この章では、オペレーティングリース取引の出資対象となる「航空機」、「船舶」、「コンテナ」について、それぞれ耐用年数をお伝えします。
航空機
航空機は、節税目的のオペレーティングリース取引の中でも、特にメリットが大きい取引対象です。
購入代金が莫大な金額であることから、減価償却費として計上できる金額(節税メリット)が大きいためです。
そんな航空機の法定耐用年数は、最大離陸重量(離陸できる総重量の最大値)によって異なります。
最大離陸重量別の航空機の法定耐用年数は、下記の通り設定されています。
- 最大離陸重量が130トン超の航空機:10年
- 最大離陸重量が5.7トン超〜130トン以下の航空機:8年
- 最大離陸重量が5.7トン以下の航空機:5年
- その他(ヘリコプターなど):5年
船舶
航空機や後述するコンテナと比べるとメリットは少ないものの、船舶もオペレーティングリースの投資対象となり得ます。
値動きが激しいため、中古での売却時に想定よりも得られる収益が少なくなるリスクがある点に注意が必要です。
そんな船舶は、船の構造や重量(総トン数)などの項目により、耐用年数が細かく設定されています。
下記にて、オペレーティングリース取引で用いられる主要な船舶の耐用年数を示しているので参考にしてください。
⑴船舶法の適用を受ける鋼船
- 総トン数が500トン以上の漁船:12年
- 総トン数が500トン未満の漁船:9年
- 総トン数が2,000トン以上の油そう船:13年
- 総トン数が2,000トン未満の油そう船:11年
⑵その他
- 薬品そう船:10年
- 総トン数が2,000トン以上の船舶:15年
- 総トン数が2,000トン未満のしゅんせつ船及び砂利採取船:10年
- 総トン数が2,000トン未満のカーフェリー:11年
- 総トン数が2,000トン未満のその他船舶:14年
コンテナ
少額(1,000万円)からの投資が可能である点から、コンテナもオペレーティングリース取引の対象として人気の投資商品です。
そんなコンテナの法定耐用年数は、長さによって異なります。
具体的なコンテナの法定耐用年数を下記に示しましたので、こちらをご参照ください。
- 大型コンテナ(長さ6メートル以上):7年
- 6メートル以下のコンテナ(金属製):3年
- 6メートル以下のコンテナ(その他):2年
参考:http://www.web-seibunsha.jp/tebiki/pdf/9/pdf_mask/huroku.pdf
まとめ
賃貸借取引として行うオペレーティングリース取引では、貸手企業側で減価償却の処理を行わなくてはいけません。
減価償却費を計上する際に用いる耐用年数は、投資対象の資産によって異なります。
したがって、減価償却費を計算する際には、まずはリース資産の耐用年数を調べましょう。